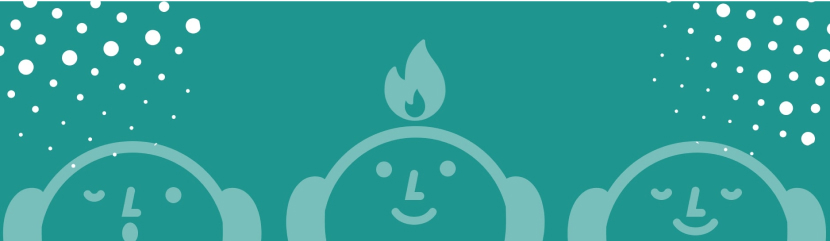目次
しかし、ヨーロッパNo.1ポッドキャストとも称される『The Diary of a CEO(あるCEOの日記)』が、米英の主要な映画館でプレミア上映を行うというニュース(出典: https://www.prnewswire.com/news-releases/regal-announces-its-first-ever-podcast-on-the-big-screen-world-exclusive-premiere-of-the-diary-of-a-ceo-with-steven-bartlett-and-global-music-star-louis-tomlinson-302571243.html)は、従来の広告やマーケティングの常識を覆す、新しい戦略の幕開けを示唆しています。
デジタルで築いたコミュニティの熱量を、いかにしてリアルな体験へと繋げ、強力な顧客エンゲージメントを生み出すか。これは、新しい顧客接点やマーケティング手法を模索する多くの企業担当者にとって、重要な問いです。
本記事では、この画期的な事例を基に、デジタルとリアルを融合させた最先端のメディアミックス戦略、そしてイベント協賛や体験型コンテンツの新たな可能性について解説します。
1. ポッドキャストの劇場上映が、企業のコンテンツマーケティングに示唆すること
1-1. なぜ「体験」の提供が重要なのか
スマートフォン一つで、いつでもどこでもアクセスできるのがデジタルコンテンツの強みです。しかし、消費者の価値観はモノ消費からコト消費へ、そして現在は「体験価値」そのものを重視する時代へとシフトしています。
事実、世界のポッドキャスト・ライブイベント市場は急速に成長しており、2033年には100億ドル規模に達すると予測されています。これは、リスナーが単なる情報のインプット(利便性)だけでなく、クリエイターや他のファンと熱量を共有する「体験」にこそ、より強い動機付けを感じていることを示しています。
デジタルコンテンツがどれほど普及しても、人々が物理的な空間に集まり、同じ瞬間を共有したいという根源的なニーズは消えません。『The Diary of a CEO』の戦略は、このニーズを的確に捉えています。
1-2. 広告モデルからコミュニティモデルへのシフト
従来のメディア戦略は、広告枠を購入し、いかに多くの人にリーチ(到達)させるかという「広告モデル」が主流でした。しかし、デジタル広告が溢れかえる現代において、その効果は相対的に低下しています。
そこで重要になるのが、自社のコンテンツに熱狂するファンを集め、その繋がりを深める「コミュニティモデル」への転換です。
『The Diary of a CEO』の劇場上映は、広告出稿による短期的な収益ではなく、映画館というプレミアムな場で「共同体的で、文化的な瞬間」を共有することにより、ブランドとファンの長期的な関係性を構築することを目的としています。これは、リーチ獲得から顧客エンゲージメント(深い関係性)の獲得へと、マーケティングの軸足が移っていることを象徴しています。
2. 事例研究:『あるCEOの日記』はいかにして巨大なブランド資産を築いたか
2-1. ターゲットを惹きつける一貫した世界観とコンテンツの品質
『The Diary of a CEO』の成功は「深さが広さを生む」戦略に基づいています。短いコンテンツが主流となる中、あえて2〜3時間に及ぶ深い対話を提供し続けてきました。
この番組の実態は、単なる「ポッドキャスト」ではなく、たまたま音声のみのバージョンも存在する「YouTube番組」です。高品質な映像制作に初期から投資し、視覚的にも魅力的なコンテンツを提供し続けてきました。
この一貫した高品質なコンテンツが受動的な視聴者ではなく、エンゲージメントが極めて高い「スーパーファン」を育成したのです。
2-2. ホストのパーソナルブランディングが企業にもたらす効果
この番組の強力なブランド資産は、ホストであるスティーブン・バートレット氏個人のパーソナルブランディングと不可分です。
彼は単なるインタビュアーではなく、自身の成功体験や脆弱性をさらけ出す「一人の人間」として、視聴者と深い信頼関係を築いています。この強い共感が、コンテンツへの忠誠心(ロイヤリティ)を生み出しています。
企業がオウンドメディアを運営する際も、単なる情報の羅列ではなく、こうした「顔の見える」パーソナルブランディングを取り入れることが、視聴者との関係構築において非常に有効です。
2-3. 視聴者の心を掴むストーリーテリングの技術
バートレット氏の番組は、ゲストの人生の浮き沈みや葛藤を引き出す、卓越したストーリーテリング(物語を語る技術)によって構成されています。
人々はデータや事実よりも、感情を揺さぶる物語に強く惹きつけられます。劇場上映されたルイ・トムリンソン氏の回では、彼の生い立ち、グループ時代、そして家族の喪失といったパーソナルな物語が語られました。
このような深いストーリーテリングこそが、視聴者を単なるリスナーから熱心なファンへと変え、ブランドへの強い愛着を醸成する鍵となります。
3. 「視聴者」を「熱狂的コミュニティ」に変える具体的な方法
3-1. デジタルとリアルの融合:ライブイベントがエンゲージメントを高める仕組み
『The Diary of a CEO』は、2021年からライブツアーを開始し、デジタルで築いたコミュニティをリアルな場へと導いてきました。
オンラインで時間をかけて醸成された熱狂的なコミュニティこそが、ライブツアーや劇場チケットのようなプレミアムなオフライン体験に対価を支払う原動力となります。
デジタルの「一対多」の放送を、リアルの「多対多」の共有体験へと転換させる。このOMO(Online Merges with Offline)戦略こそが、どんなデジタル施策よりも深いブランドへの忠誠心を育むのです。
3-2. 「劇場上映」がもたらすブランドへの圧倒的な没入体験
今回の劇場上映は、ライブイベントをさらに進化させたものです。ホストのバートレット氏は、この狙いを「共同体的で、文化的な瞬間」の創出にあると述べています。
あえて「その日、その場所でしか見られない」という希少性を創出する「アポイントメント・トゥ・ビュー(予約視聴型)」戦略により、コンテンツの価値を高めています。
映画館というプレミアムな「大スクリーン」で、集中した環境でコンテンツに没入する体験。それは、YouTubeでの無料視聴では得られないレベルの威信と文化的重要性をブランドに与え、参加者の記憶に強く刻まれます。
4. 自社のオウンドメディア戦略にどう活かすか
この事例から、日本の企業はどのようなヒントを得られるでしょうか。
4-1. 顧客の共感を生むテーマ設定とペルソナの深掘り
まずは、自社のターゲット(ペルソナ)が何に悩み、何に情熱を感じるのかを深く理解することが出発点です。
『The Diary of a CEO』が成功したのは、ビジネスの成功譚だけでなく、失敗、精神的な葛藤、人間関係といった、誰もが共感しうる普遍的なテーマを深く掘り下げたからです。
自社のオウンドメディアも、製品の機能説明に終始するのではなく、顧客が共感できるストーリーや世界観を一貫して発信することが、ファンマーケティングの第一歩となります。
4-2. 動画コンテンツとの連携によるエンゲージメントの飛躍的向上
データによれば、今やYouTubeはポッドキャストの消費と発見においてNo.1のプラットフォームであり、特に新規利用者の64%が「ビデオファースト」であると報告されています。
『The Diary of a CEO』が劇場上映というリアル体験へスムーズに移行できたのも、高品質なビデオポッドキャスト(動画)戦略があったからです。
テキストベースのオウンドメディア(ブログなど)を運営している企業も、その内容を動画コンテンツ(YouTubeやウェビナー)と連携させることで、視聴者のエンゲージメントを飛躍的に高めることが可能です。
4-3. オンラインセミナーから始めるコミュニティ形成の第一歩
『The Diary of a CEO』のような大規模な劇場上映は、すぐに真似できるものではありません。しかし、その本質は「デジタルで築いた関係性を、リアル(あるいは限定的な体験)で強化する」ことです。
多くの企業にとって、その第一歩となり得るのがオンラインセミナー(ウェビナー)や、小規模なミートアップです。
まずは自社のオウンドメディアやウェビナーのファンを集め、限定的な情報を提供する場や、参加者同士が交流できる場を設ける。このスモールスタートこそが、将来の熱狂的なコミュニティ形成に繋がります。
5. まとめ
『The Diary of a CEO』の劇場上映は、マーケティング戦略が「広告枠の購入」によるリーチ獲得から、「熱狂的コミュニティ」を巻き込む体験の創出によるエンゲージメント獲得へと、決定的にシフトしていることを象徴しています。
デジタル(ポッドキャストや動画)で熱量を高め、リアル(イベント)で特別な体験を提供する。このメディアミックスとOMOの考え方は、イベントマーケティングや顧客エンゲージメントのあり方を根本から変える可能性を秘めています。
自社において、オンラインで築いた顧客との関係性を、どのようなオフラインの「特別な体験」に繋げられるか、検討する価値があるでしょう。
参考情報
- The Diary Of A CEO podcasts hits the big screen with Cineworld (https://podcastingtoday.co.uk/the-diary-of-a-ceo-podcasts-hits-the-big-screen-with-cineworld/)
- Regal Announces Its First Ever Podcast on the Big Screen: World Exclusive Premiere of “The Diary Of A CEO” with Steven Bartlett and Global Music Star Louis Tomlinson (https://celluloidjunkie.com/wire/regal-announces-its-first-ever-podcast-on-the-big-screen-world-exclusive-premiere-of-the-diary-of-a-ceo-with-steven-bartlett-and-global-music-star-louis-tomlinson/)
- Regal Announces Its First Ever Podcast on the Big Screen: World Exclusive Premiere of “The Diary Of A CEO” with Steven Bartlett and Global Music Star Louis Tomlinson (https://www.prnewswire.com/news-releases/regal-announces-its-first-ever-podcast-on-the-big-screen-world-exclusive-premiere-of-the-diary-of-a-ceo-with-steven-bartlett-and-global-music-star-louis-tomlinson-302571243.html)
- Get Ready to Run to Cineworld to watch the exclusive screening of Louis Tomlinson’s Diary of a CEO interview (https://www.cineworld.co.uk/static/en/uk/blog/watch-exclusive-cineworld-screening-louis-tomlinson-diary-of-a-ceo-interview)
- The Diary of a CEO Live Tickets | Tours & Dates | ATG Tickets (https://www.atgtickets.com/shows/the-diary-of-a-ceo-live/)
- Tour – Steven Bartlett (https://stevenbartlett.com/tour)
- The Diary of a CEO – Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Diary_of_a_CEO)
- Steven Bartlett (businessman) – Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Bartlett_(businessman
- Why The Diary Of A CEO Founder Turned Down A $100M Deal To Build A Podcast Empire (https://www.forbes.com/sites/alexyork/2025/04/19/why-the-diary-of-a-ceo-founder-turned-down-a-100m-deal-to-build-a-podcast-empire/)
- Stephen Bartlett’s Diary of a CEO hits one billion milestone (https://podnews.net/press-release/doac-one-billion)
- Podcast Live Events Market Size, Share, Trends & Growth (https://growthmarketreports.com/report/podcast-live-events-market)
- Podcast companies turn to live events to capture growing advertiser spend (https://digiday.com/media/podcast-companies-turn-to-live-events-to-capture-growing-advertiser-spend/)
- The 2025 State of Video Podcasts (https://www.sweetfishmedia.com/blog/the-2025-state-of-video-podcasts)
- The Rise of Video Podcasts: Why YouTube is Winning the Podcasting War (https://www.reprtoir.com/blog/video-podcast)
- New Podcast Consumers Actively Engage with Video Content (https://www.edisonresearch.com/new-podcast-consumers-actively-engage-with-video-content/)
Download 番組事例集・会社案内資料
ぴったりなプランがイメージできない場合も
お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
マイク選び・編集・台本づくり・集客など、ポッドキャスト作りの悩み・手間や難しさを誰よりも多く経験してきました。そんな私が皆様のご相談をメールやオンラインMTGで丁寧にお受けいたします!